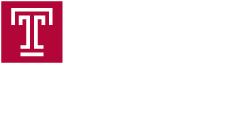教務担当副学長のジョージ・ミラーが、テンプル大学ジャパンキャンパス(TUJ)と彼の東京での新生活について月に一度のコラムをお届けします。今回は、居心地の良い領域の外に快適さを探すことについて書いています。
何週間か前、ある学生が私のオフィスへやって来てソファに座ると、床を見つめ始めました。
私は彼に少し時間をあげて、そして質問しました。
「学校はどう?」
彼は目を合わせずに何かを呟きました。初めのうちは会話するのが困難でした。
最終的に私は、その場の空気を和ませるために学校についてのジョークを言いました。何を言ったのか覚えていないのですが、とてもくだらないことだったのは確かです。もちろん、意図的にそうしました。すると彼は、ようやく心を開いてくれました。
彼はクラスで問題を抱えていました。自分の部屋で、ずっと1人きりで時間を過ごしていました。東京にいる時間を有効に使わず、嘆き悲しみ、TUJに友達もいませんでした。
うまく溶け込めない、と彼は言いました。
「ああ、私もどこにも溶け込んでいないよ」と私は言いました。「今まで一度もない。でも私を見てごらん。副学長をやっているんだ」
面白おかしく言ったつもりでしたが、実際のところ、それが真実なのです。
私は今まで、人種、宗教、民族、政治などを主張するような団体の社会的アイデンティティを持ったことがありません。公文書にサインする時も、ほとんどの場合「その他」にチェックを入れます。

私はペンシルベニア州チェスター出身の日本人と白人のハーフです。子どもの頃、母はウェイトレスとして働き、父は車を売っていました。家に1人残された私は、妄想にふけっていました。読書とドリトスを食べることに時間を使い過ぎたひとりっ子でした。
常に近しい友人はいましたが、グループに属すことや大勢に従うことは自分の存在において大きな要素ではありませんでした。溶け込みたいという願望もありませんでしたし、他人が自分をどう思うか気にすることもありませんでした。私が知る一番重要な人物は、私の頭の中にいました。
溶け込まないことが、実際には、居心地が良かったのです。

過去7年間、私はフィラデルフィアで『JUMP』という地元密着の音楽雑誌を出版していました。場違いだな、と感じることはよくありました。コンサートに行くと、自分だけがアフリカ系アメリカ人ではないことはしょっちゅうでしたし、どんなショーでも、ほとんど毎回、私が一番年上でした。
ある時、コロラドで開催されたミュージック・カンファレンスに出席したのですが、そこにはアメリカ中から流行の仕掛け人が集まっていました。テキサスでライブ会場を経営している、大きな体にタトゥーをした、あごひげのある男性が、私が出席しているのを見て驚いていました。なぜか理由を聞くと、こう言いました。「君が共和党の髪型をしているからさ」
2年前、友人のバンドのミュージックビデオ制作に参加したことがありました。西フィラデルフィアの古いビクトリア朝のテラスハウスの居間にバンドセットが組まれました。私ははじめ、後ろに立って展開を見ていたのですが、もっと良く見たくなり、上から見られるように階段の中ほどまで上がりました。
そこに立って、下で観客がモッシュしているのを見ている私に、ぶつかってきた人が言いました。「君はここに来るはずだったのか?」
ボタンダウンシャツを着た中年男がパンクのライブに来ているのは奇妙に見えたのでしょう。ですが、あまりに楽しくて、気にしたり返事をしたりすることはできませんでした。最後には、私はバンドに名前を呼ばれて階段を降り、観客の中に飛び込んでいました。あれは最高でした。
長年にわたって、私は多くの職に就いてきました。フォトジャーナリスト、ニュースレポーター、コラムニスト、出版者、教師、副議長など。ほとんどの人は、私に会った理由をもとに私のことを覚えています。私はいつも、ある人にとっては写真の人であり、ある人にとっては『JUMP』の人なのです。

私といえば、フィラデルフィア、ジャーナリズム、Mookieの3つを思い出す人がほとんどです。ところが、私が今暮らしているのは東京ですし、現在、ジャーナリズムに携わっていません。また、16歳のシーズー犬のMookieは今もフィラデルフィアにいます。東京への移動は、小さく、老いた彼の心臓には酷だと思われたからです。
大きな何かに属したことは一度もない、ということは別にして、私は新しい人生、新しいアイデンティティを、ゼロからスタートさせたところです。
ですから、溶け込めない、と学生が話し始めた時、私は理解しました。
私たちは1時間ほど話しましたが、目が合ったのは数回でした。何の結論も出ませんでしたし、どのように孤独を乗り越えるのか、どのように疎外感と闘うのか、そういった状況のもとでどのように大学で成功するのか、明確なアドバイスは本当にありませんでした。
ですが、会話は実りのあるものでした。人生を楽なもののように見せる人もいるけれど、彼らがどんな事に取り組んでいるか、私たちは気づいてさえいないかもしれない、ということを説明しました。また、自分自身の中に幸せを見つけること、他人が期待することに自分をはめ込まないことについて話しました。
そして、自分がすべきことをするように伝えました。彼の最大の妨げとなるのは彼自身です。自分自身を窮地に追い込むべきではありません。
ようやく家にたどり着いた時、ガールフレンドにこのことを話しました。
「なぜ彼はあなたのところに来たの?」と彼女は聞きました。「カウンセラーはあなたの仕事ではないわよね?」
その質問に悪意はなく、妥当なものでした。彼女はパターンに気づいたのです。
彼女は言いました。「そういった人たちは、なぜ毎回あなたを見つけるのかしら」そして、米国本校では、様々な問題と闘う人にとって私がマグネットのような存在だったと付け加えました。
「どうだろう」私は答えました。「彼らと共鳴しているだけだと思う」
もしかすると、私はどこかに溶け込んでいるのかもしれません。