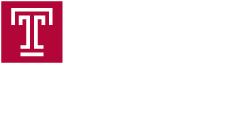文:新井雄歩(国際関係学科3年)
9月20日、テンプル大学ジャパンキャンパスが主催するイベントで、小説『コンビニ人間』の著者である村田紗耶香さんと、その英訳を担当した竹森ジニーさんの講演を聴く機会があった。以前に『コンビニ人間』は読了済みであり、今回のイベントはとても楽しみでもあった。イベントは、会場の壇上で村田さんとジニーさんが質問に答えるという形式で行われ、小説の内容に留まらない様々な質問がなされた。
初めに、『コンビニ人間』の主人公である古倉恵子はどの様にして生まれたのかという質問がなされ、村田さんは、古倉恵子という人物について次のように語った。作中において恵子は、齢三十半ばになってもコンビニエンスストアで働いており、周りの人物に絶えず指摘を受ける。特別悪いことをしていないのに周囲からは、なぜなのか、と疑問を投げかけられる、そんな人物が書きたかったと答えた。この答えに小説『コンビニ人間』の根幹を成すテーマが込められている。普通であること、周りと同じであることを暗に強要される現代日本社会の風潮に対する問題提起である。村田さんは後の回答の中で、現在の日本の社会において、コンビニ店員は差別される職業だと感じていた、とも述べている。自身の、コンビニ店員として働く体験に基づいての感想である。普通であることから外れることによって感じる重圧を、コンビニエンスストアとその店員という、どこか閉鎖的で特殊な環境を舞台に表現したのだ。
更に続く質問で、普通をどう定義するのかという質問に対して、村田さんはこう答える。執筆を始めた当初は、周囲を全く気にしない古倉恵子こそが普通でないのであり、異質な人物なのだと感じていたが、次第に恵子を変人だという周りこそが狂っているのだと思うようになったと。狂っているとは即ち、自分達は普通に就職して働いているのであるから、コンビニ店員であるところの恵子を裁いてよい、という無自覚の意識そのものである。村田さんはこの意識を、普通に隠された化け物性と呼んだ。村田さんが『コンビニ人間』を通して浮彫にしたかったのは、この化け物性を帯びた普通という社会通念であると感じた。

小説『コンビニ人間』が日本国内で話題になり、多くの人の共感を呼ぶのは想像に容易い。累計百万部を超える話題作になりえたのも、それだけ多くの人が多かれ少なかれ、村田さんのいうところの化け物性に共感したからであろう。
手元の文庫本に目をやると、その帯には24カ国語に翻訳決定と書かれている。『コンビニ人間』は、他の文化圏の人にはどう受け入れられるのだろう。ジニーさんは、『コンビニ人間』の翻訳において、人間という単語をどう翻訳すべきかとても悩んだと語った。作中において、古倉恵子は最終的にコンビニ店員に戻るという選択をする。村田さんは、恵子は最終的に人間ですらなくなったのだというのだから、その英訳は簡単なことではなかったのだろうことも伺えた。更に、村田さんは『コンビニ人間』はどうして世界中で受け入れられるに至ったのか、と問われると、古倉恵子とその周囲の登場人物の関係性には普遍性があると語った。英題こそ “Convenience Store Woman”、つまりコンビニエンスストアの女性であるが、テーマは男女の性別ではなく、周囲からの社会的なプレッシャーにあるのだ、とも語った。しかし同時に、やはり日本の読者の反応と他の文化圏の読者の反応は違っていたとも語った。日本のコンビニという場所は日本文化特有のものであり、その文化そのものを楽しむ読者も多くいるのだという。今回のイベントにおいて、小説とその翻訳の難しさを再認識させられた。
しかしながら、最終的にコンビニ人間という生き物に成ってしまう古倉恵子に対する感想は、原文を読んだ読者のものも、翻訳版を読んだ読者のものも違ったものになるのは道理である。恵子を面白い人間と捉えるのも、不気味なクリーチャーと捉えるのも読者次第である。自分にとって古倉恵子とは、他者からの圧力をものともしないヒーローそのものであった。物語終盤、コンビニ店員に戻る決断をした後も、それは変わらず恵子自身の意志であり、強い人物として映る。多くの読者が恵子のようにはなれないという感想を残す、と語った村田さん。自分もその一人である。